皆さんこんにちは。奨学金ブロガーのむーさんです。
このたび――奨学金1000万円を完済しました。
返済生活、丸7年で卒業です。
ネットやSNSでは「繰上返還は賛成」「いや、しないほうがいい」と議論が割れます。私は早期完済を選びましたが、そこに至るまでに数字と現実の生活を何度も突き合わせて考え抜きました。
この記事では、以下について解説しています。
- 繰上返還をするメリットとデメリット
- 繰上返還をしない場合に潜む落とし穴
- そして意外と知られていない「機関保証制度の保証料返戻」について
私の体験を交えて整理しています。実際に完済した人間のリアルな視点からお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
繰り上げ返還は「できるならしたほうがいい」
最初から結論を言ってしまうと、繰上返還は資金的に可能であればした方が良いです。
もちろん、繰上に回せる余剰資金がない場合は無理をする必要はありませんが、「あえてしない」選択肢をとるときには慎重な判断が必要です。
否定派の主張としてよくあるのは次のような意見です。
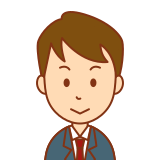
低金利(または無利子)の奨学金を返すより、NISAなどで投資をした方が効率的。繰上するのは損!
一見もっともらしいのですが、この考え方には落とし穴があります。
貧困が人を馬鹿にする?奨学金は少額に抑えて返済を優先すべき理由
の記事でも返済を優先した方が良い理由について解説しておりますので参考にしてください。
落とし穴1:投資は必ず儲かるとは限らない
金融投資は「やれば必ず利益が出る」ものではありません。
特に2025年現在は、オルカンなどのインデックスファンドをNISAで購入して大きな含み益を得ている人も多いですが、相場には必ず暴落局面があります。
上昇相場が続いていると「投資=必ず増える」と錯覚しがちですが、いざ下落すると心理的ストレスで売れず、結果的に奨学金返済も滞りがちになるリスクがあります。
💡 投資を否定するわけではありませんが、借金返済とのバランスを取ることが重要です。

金融投資を全くすべきでないということでなくバランスが大事。
返還の比重が高いほうがちょうどいいと思うよ。
落とし穴2:金融投資は資金を未来に先送りする行為
投資で増えたお金を「利益確定して返済に回せばいい」と考える人もいますが、現実には次の問題があります。
- 短期的に暴落が起きれば、売却するどころか含み損で身動きが取れない
- 含み益があっても「もう少し増えてから…」と売却を先延ばししてしまう心理的ハードル
その結果、毎月の返済は続いているのに手元のキャッシュフローは改善しないという矛盾が起こりがちです。
落とし穴3:保証料の返戻を見落としている
意外と知られていないのが、機関保証制度を利用している人は繰上返還で保証料が一部返金されるという点です。
- 奨学金振込額から毎月自動で天引きされる「保証料」
- 繰上返還をすると未経過分が返戻される仕組み
例えば私の場合、約23万円の保証料が戻ってきました。
これは投資のように「増えるかどうか分からないお金」ではなく、繰上返還するだけで確実に戻ってくるお金です。
繰上返還をしないと、この返戻を取り逃してしまい、実質的に損をしている可能性があります。
忘れるべからず!機関保証の返還金
私の場合、日本学生支援機構(JASSO)の第一種・第二種奨学金をあわせて約1,000万円借りていました。親族に保証人を立てることが難しかったため、機関保証制度を利用していました。
完済を決めた大きな理由のひとつが、保証料の返戻金です。
「いま完済したら、どのくらい保証料が戻ってくるのか」を事前に確認したうえで、繰上返還を実行しました。
期間保証の返還金額の確認方法
同じように機関保証制度を利用している方は、公益財団法人 日本国際教育支援協会 機関保証センターに問い合わせるのが最も確実です。
| 機関名 | 公益財団法人 日本国際教育支援協会 機関保証センター |
| 電話番号 | 03-5454-5271 |
なお、問い合わせる場合、奨学生番号が必要になります。
私の場合は、
- 第二種奨学金を完済すると → 約20万円
- 第一種奨学金を完済すると → 約3万円
と、合計で約23万円が返戻されると教えていただきました。
期間保証の返還金はいつ戻って来るの?
注意点として、保証料は完済直後にすぐ戻ってくるわけではありません。
私の場合、返還から2〜3か月後に通知書が届き、その後に銀行口座へ振り込みがありました。
つまり、「返戻金をすぐに生活費に回す」という使い方はできないため、余裕資金を持ったうえで繰上返還を実行することが大切です。
繰上返還することにデメリットは?
繰上返還には大きなメリットがあると考えていますが、同時にデメリットも存在します。
- 一時的に手元の現金が減る
- 投資と比べて期待利回りが低い場合がある
繰上返済を行うと、手元資金は当然減ります。生活防衛資金が十分に確保されていない状態で実行すると、日々の生活や突発的な出費に対応できず、かえって家計が苦しくなる危険もあります。そのため、余裕資金があるときに実行することが前提です。
また、金融投資に比べると利回りで劣るケースもあります。ただし、数字だけでは測れないメリット――例えば「毎月の返済が消えることでキャッシュフローが劇的に改善する」「心理的な負担が軽減される」――を考えれば、多くの人にとって繰上返還は十分合理的な選択肢となるでしょう。

奨学金を完済したことで、毎月の返済がなくなりキャッシュフローが大きく改善しました。精神的にも肩の荷が下りて、気持ちが本当に楽になりました。
まとめ:繰上返還は「得する選択肢」
奨学金の繰上返還は、利回りだけを考えると投資に劣るように見えることもあります。しかし、次の点を踏まえれば「実質的に得をする」ケースが多いといえます。
- 投資のリターンは不確実であり、暴落リスクや売却の心理的ハードルも存在する
- 機関保証を利用している場合、保証料返戻という確実なお金が戻ってくる
- 毎月の返済がなくなることで、キャッシュフローが改善し、精神的な安定も得られる
つまり、余裕資金があるなら繰上返還は積極的に検討すべき選択肢です。
返済を終えることで手に入る「自由なお金」と「心の安心感」は、利回りの数字以上に大きな価値がありますよ。
この情報が皆様の奨学金返済の一助になれば幸いです。
それでは。
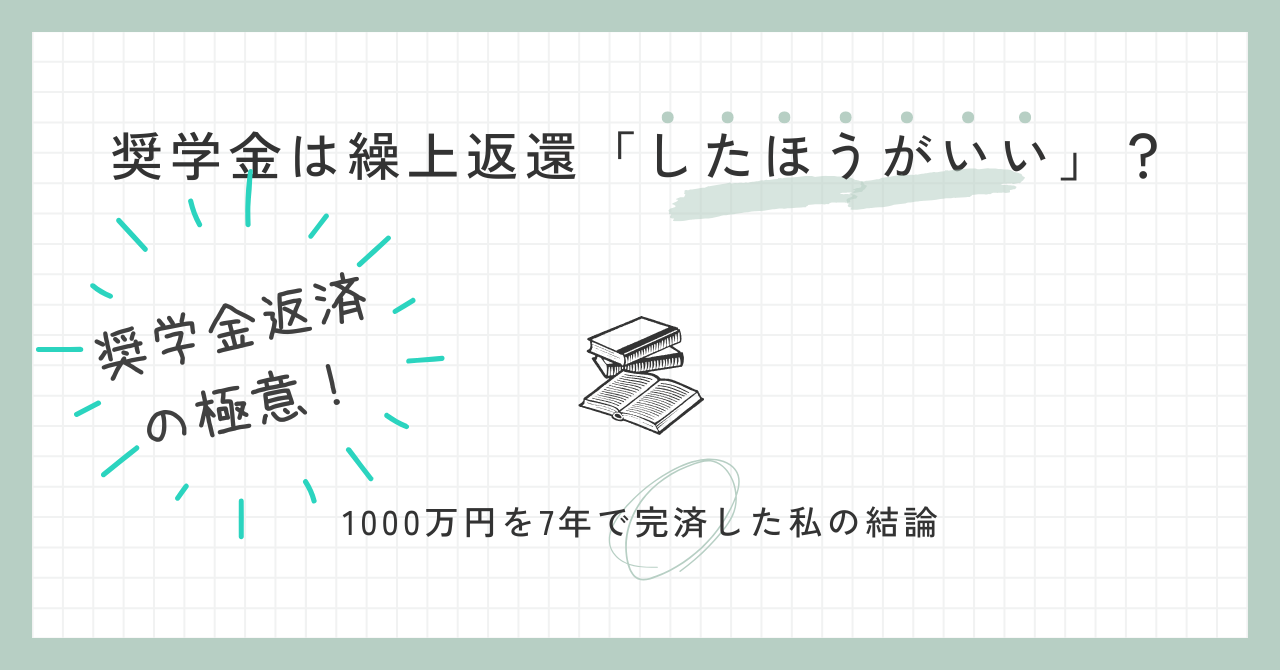
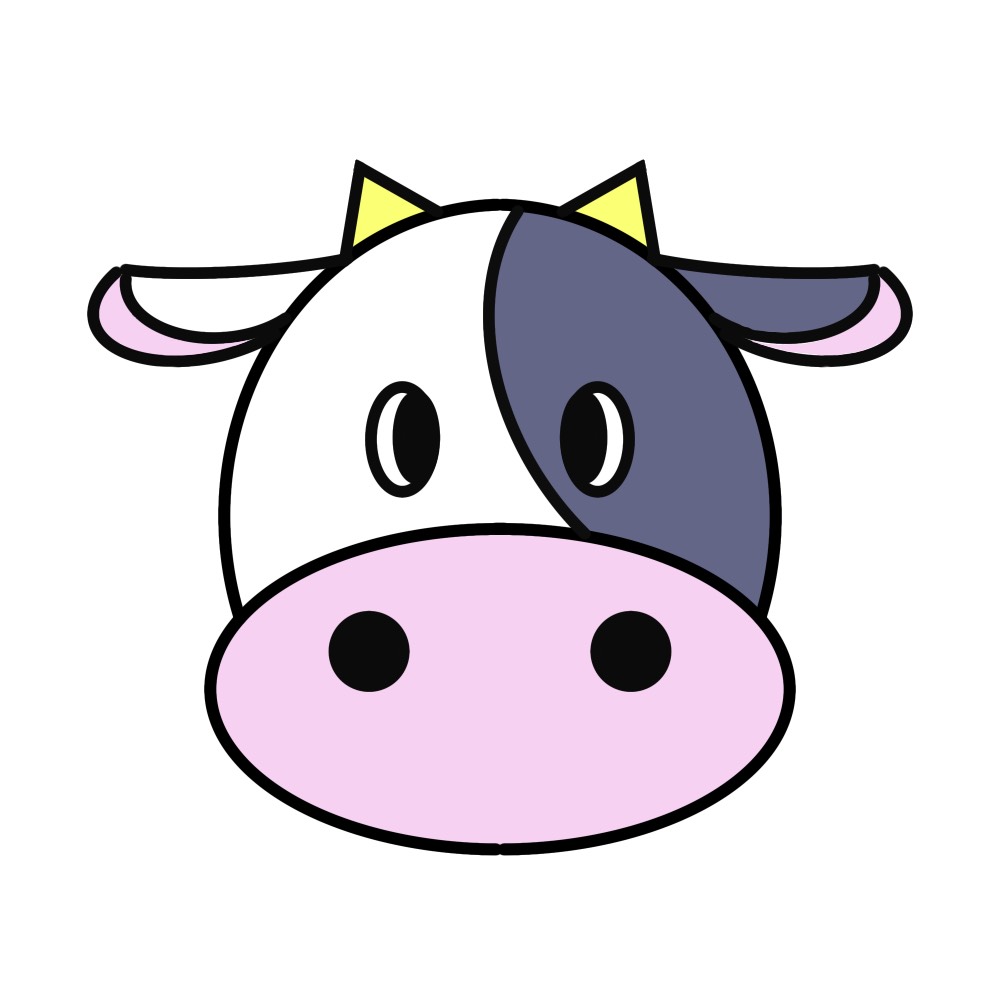
コメント